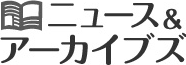札幌弁護士会犯罪被害者支援委員会
第1 はじめに
犯罪被害者支援活動の情報や経験の共有を目的として、毎年、日本弁護士連合会、開催地の弁護士会連合会及び各弁護士会による主催で、犯罪被害者支援活動の事例報告やパネルディスカッション等を内容とする犯罪被害者支援全国経験交流集会が行われています。
当会の犯罪被害者支援委員会からも委員が毎年出席しており、今年は2024年1月26日に沖縄県那覇市にて開催された犯罪被害者支援全国経験交流集会に複数の委員が出席しました。
第2 2023年度の犯罪被害者支援全国経験交流集会の内容
沖縄弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長、九州弁護士会連合会理事長による開会挨拶の後、第1部は被害者ご遺族による基調講演、第2部は被害者支援弁護士による事例報告、第3部は精神科医による講演、第4部は講演者と事例報告者による「二次被害を予防するための方策及び弁護士の支援の在り方」をテーマとしたパネルディスカッションが行われました。このうち、第1部の基調講演、第3部の精神科医による講演、第4部のパネルディスカッションについての要旨をご案内します。
第3 被害者ご遺族による基調講演について
- 2019年に東京の東池袋で発生した、高齢運転者による交通事故によって妻子を亡くされた松永拓也氏と、妻の実父の上原義教氏のお二人の被害者ご遺族による基調講演が行われました。
- 松永拓也氏の講演テーマは「私が経験した二次被害」でした。
松永氏は、交通事故後、SNSによる二次被害を受けました。民事裁判が始まった頃からX(旧Twitter)で誹謗中傷を受け始めるようになったとのことで、警察に被害届をし、刑事事件として起訴後、有罪となった事例の報告もありました。
報告された事例の投稿者は、「承認欲求があった」、「イライラしてやった」、更には「違う遺族に対し投稿したものだ」、「スマホが誤作動した」などの弁解をしていたそうです。松永氏はSNSやYAHOO!コメントなどでは、事実に基づかない投稿によって非常に傷つけられたと述べられていました。
SNSだけでなく、身近な人からも「宝くじに当たったみたいで羨ましい」といった心ない言葉をかけられたり、他にも、損害賠償金は高齢の加害者本人が支払うものと思い込んだ人から誹謗中傷を受けることもあったため、損害賠償金は保険会社が支払うということを発信したこともあった、とのことです。
松永氏が繰り返し述べられていたのは、「お金が欲しい訳ではない」、「被害者の多数は被害に遭う前に戻れるならお金はいらないはず」、「心の折合いが付けられない」、「お金で責任を負ってもらうしかない」ということです。多くの被害者が苦しむ現状を述べられていたことが印象に残りました。
最後に松永氏は、「SNSを見なければいいのではないか」、「投稿を放置しておけばいいのでないか」という声もあるが、被害者の現実を知ってもらうために敢えて発信をしてきたと述べられました。松永氏が発信を続けている理由は、これからの被害者がSNSの誹謗中傷によって萎縮をして欲しくないという思いから、とのことです。
参加した委員も、被害者支援を行っている弁護士として、被害者に対するSNSによる誹謗中傷に対する被害相談は避けられない問題であり、問題の深刻さと解決の困難さを痛感しました。 - 上原義教氏の講演の第一声は、「今でもすっきりはしていない」、「今もつらい」という現在の心境を表すものでした。続けて上原氏は、「裁判中は東京に行ったり来たりして、忙しさに紛れていたが、今の方が苦しくて眠れない」、「娘の写真をポケットに入れたり、娘のことを考えたりしてしまう」と声を詰まらせながら述べられました。
上原氏は「裁判は長すぎる」とも述べており、「早く裁判が終わって欲しい」、また、「何も悪いことをしていないが家族みんなが苦しめられ、今も苦しんでいて、解放されることはない」、「生きていくことが難しい」、「『生きる』ということは力がいるし、乗り越える源が必要となる」という被害者の心情を時折声を詰まらせながら述べられました。
また、裁判は東京地方裁判所で開かれましたが、上原氏は飛行機で出向くこととなることから、経済的・時間的な負担も大きかったということでありました。そのようなご自身の実体験を踏まえ、被害者の負担を軽減するための制度があればよいのではないか、といったご提言もありました。
上原氏は、事故のことを振り返って話すことは辛いが、事故後に必要な 支援は何かを伝えたいと思い、初めは断ったが講演を引き受けることにしたとのことでした。
第4 精神科医による「二次被害を防ぐ」と題する講演について
- 性暴力被害者支援に取り組んできた強姦救援センター・沖縄(REICО)のスタッフも経験された精神科医佐村瑞恵医師による「二次被害を防ぐ」と題する講演がありました。
- 人が突然犯罪の被害にあった場合、命を守るための原始的な反応としてフリーズするのが普通であること、被害直後の反応として、状況が理解できない、恐怖や緊張、抑うつ、過活動、不眠などの症状が現れることがあり、安全な状況が続くと症状は消失していくこともあるが、3日以上このような症状が続くと、急性ストレス障害(ASD)、1か月以上続くと心的外傷性ストレス障害(PTSD)と診断され、それに加えて、①感情のコントロールができない②自己に対する否定的な考え③対人関係の困難などの症状がある場合は複雑性PTSDと診断されること等が述べられ、特に児童虐待の被害者の複雑性PTSDの問題が指摘されました。
このような犯罪被害者に現れる症状を理解した上で、二次被害を防ぐためには、被害者の証言は変遷するものだということを理解し(覚えていなくて当たり前)、「なぜ逃げなかったの?」「なぜ車に乗ったの?」などと相手を責めない、「そのうち忘れるよ」などと被害を軽視しているかのようなことを言わない、「かわいそうに」などと同情した言動をしない、「私に任せて」などと主導権を握るような言動をしないことなど留意点が指摘され、参加した委員も気をつけるべき点が多いと痛感しました。
第5 パネルディスカッションについて
- 第4部のパネルディスカッションでは、登壇者により、様々な場面での二次被害の防止について意見が交わされました。
- 1つ目のテーマとして取り上げられたのは、メディアにまつわる二次被害でした。
いわゆるメディアスクラムについて、事故直後の絶望感の中でいつまで も自宅のインターフォンが鳴り続けたり、被害者の友人であると嘘をついてまで自宅に上がって取材しようとする記者がいたとの体験談が語られ、被害者の負担を軽減するために捜査機関が取材自粛のアナウンスをしたり、弁護士が報道対応の窓口になったりするなどの対応策の必要性が指摘されました。 - 2つ目のテーマは、SNS等における被害者に対する誹謗中傷への対応についてでした。
被害者遺族の方からは、根も葉もない噂がいつまでもインターネット上に 残り続けて拡散されていくというSNSの特性を考えると、単純に無視すればよいとも言い切れないとの意見が出されました。
議論の中で、SNSでの誹謗中傷に対しては、刑事事件としての立件等の対応を通じて、社会として抑止力を働かせていく必要があるという認識が示されました。 - 3つ目のテーマは、司法手続の中での二次被害についてでした。
刑事裁判への参加に伴う被害者の経済的・精神的な負担の軽減の必要性や、性暴力被害者に対する司法関係者の理解を深める必要性が指摘されました。 - パネルディスカッションでの議論を踏まえて、会場からも活発に質問が 出され、充実した議論を経て、パネルディスカッションが締めくくられました。
第6 さいごに
- 当会の犯罪被害者支援員会では、被害者がどこで被害に遭ったとしても同様の支援を受けることができるよう、道内全市町村に向け、2022年8月26日に札幌市内で条例制定に向けたシンポジウムを開催しました。
- 被害者の置かれている現状、特に経済的支援は不十分であり、当委員会では条例制定に向けた活動を継続させていきたいと考えています。
以上