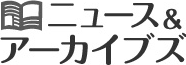※以下の記事は、北海道新聞社のどうしん電子版に2021年4月から6月まで掲載された広告記事となります。
当会が作成に協力したもので、北海道新聞社の許諾を得て掲載しております。
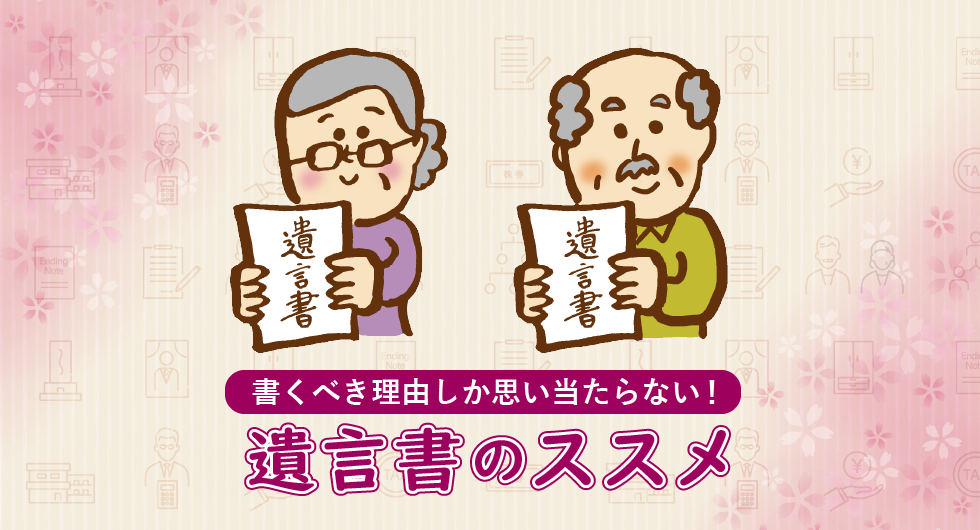
「遺言書=お金持ちや高齢者が書くもの」と思われがちですが、決してそうではありません。遺言書は、残された家族や親族が争うことなく、安心して生活していけるようにするための最後の愛情表現とも言えます。あなたの大切な財産を大切な人へ確実に手渡すために、遺言書について真剣に考えてみませんか。
遺言書がなくて困った!あってよかった!事例集
遺言書は自分の死後の財産分与に関する意思を示す法的手段です。遺言書がなかったために、わずかな遺産を巡って骨肉の争いが起こったり、事実婚のパートナーが1円も財産を受け取れなかったというケースも珍しくありません。逆に、遺言書があったおかげで財産処理がスムーズに進んだというケースも。ここではそんな事例の一部をご紹介します。
遺産の配分に関する遺言書がない
土地の相続を巡って先妻の子と後妻がトラブルに
後妻に自宅を生前贈与した夫が亡くなった後、実は建物しか贈与されていないことが判明。先妻の子どもたちが後妻に土地の財産分与を求めてきました。両者はもともと仲が悪く、夫の遺言書もなかったため、数年間争った末に土地の分筆(一つの土地を複数に分ける)や現金の分配によって決着しました。
不仲の親族がいると話がこじれやすく、問題が長期化することが少なくありません。また、土地は分筆すると地価が下がってしまうため、資産が目減りしてしまいます。財産分与の方法を明記した遺言書があればもめずに済んだことでしょう。
遺言書がなく財産の信憑性が不明
遺産が少なすぎる!疑心暗鬼で兄弟が不仲に
亡くなった父の財産が思いのほか少ないことを知った兄弟。財産の内訳や分与方法を示した遺言書がないため、お互いに「相手が勝手に親の預金を使い込んだのでは」と疑い、話し合いがこじれて仲違いしてしまいました。
わずかな財産を巡る相続争いは珍しいことではありません。むしろ肉親ゆえに感情的になりやすく、それまで仲の良かった兄弟が絶縁状態になってしまうケースもあるのです。確かな判断能力があるうちに遺言書を用意しておくことは、子どもの幸せを願う親の務めと言えるでしょう。
法定相続人がいない人の財産遺贈
遺言書のおかげで安らかに旅立ったおひとりさま
闘病中のおひとりさま。生涯独身で法定相続人となる親族もいないため、長年お世話してくれていた、いとこに全財産を譲る旨の遺言書を残して亡くなりました。 法定相続人がいない人の財産はさまざまな手続きを経て国庫に納められますが、特定の人や団体に財産を譲ること(遺贈)を希望する場合、遺言書が効力を発揮します。自分で築き上げた財産を自分が望む人へ託すことができれば、死後の憂いなく安らかに旅立てるに違いありません。
法律のプロが教える遺言書作成のポイント

遺言書は、相続人同士のトラブル防止はもちろん、法定相続人がいないおひとりさまの死後を見据えた財産処理や遺贈を行う上でも有効です。遺言書を作成する上で知っておきたいポイントを、弁護士の大町英祐先生にお聞きしました。
「もしも」に備えて元気なうちに遺言書を用意しましょう
相続を巡るトラブルは誰にでも起こりうる問題です。「うちはお金持ちじゃないから関係ない」と思っていても、自宅の土地建物や預金などを合わせると1000万~2000万円ほどの資産を持つご家庭は多いはず。相続トラブルのご相談も、これくらいの金額が非常に多いのです。
家族がいる方はもちろん、おひとりさまも例外ではありません。親兄弟や甥・姪がいれば遺産の行き先もありますが、おひとりさまが一人っ子で親も他界していれば、せっかく築いた資産が国の財産に。その手続きも容易ではなく、多くの人の手を煩わせることになります。
「もしも」に備えるという意味で、遺言は保険に似ています。たとえ若くて元気でも、いつ何があるかわかりません。体力と判断能力があるうちに財産の処分方法を考え、遺言書を用意しておくことをお勧めします。
遺言書の種類とメリット・デメリットを理解しておきましょう
民法上の遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ違いやメリット、デメリットがあります。ここでは、一般の方の利用が多い「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の特徴を見比べてみましょう。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 遺言の全文・氏名・日付を手書きし、押印する 財産目録はパソコンで作成したり通帳のコピーでも可 | 公証役場で本人が遺言内容を口述し、その内容を公証人が記述する |
| 証人 | 不要 | 2名以上 |
| 費用 | 不要(法務局保管の場合は必要) | 要 |
| 保管場所 | 自宅などまたは法務局 | 公証役場 |
| 家庭裁判所の検認 | 要(法務局保管の場合は不要) | 不要 |
| メリット | ・低コストで簡単に作成できる ・保管制度を利用した場合は紛失の恐れがなく検認手続き不要 |
・内容の不備や紛失の恐れがない ・遺言の存在と内容を明確にできる ・検認手続き不要 |
| デメリット | ・内容に不備があると無効になる ・自宅保管の場合は紛失の恐れあり ・自宅保管の場合は検認手続きが必要 |
・費用がかかる ・証人の立ち会いなどの手間がかかる ・公証人と証人に遺言の内容を知られてしまう |
相続法改正により「自分で書く遺言書」がぐっと身近に
公正証書遺言は法的効力や保管の安全性が高い反面、第三者に遺言の内容を知られてしまう上、費用がかかります。
最も手軽なのが自筆証書遺言です。従来は財産目録も含む全文を手書きしなくてはなりませんでしたが、2018年7月に相続法が改正され、財産目録はパソコンで作成したものや通帳のコピーでも認められるようになりました。
また、従来は遺言書を自宅に保管することが多く、紛失や改ざんのリスクがありましたが、20年7月より法務局に自筆証書遺言書を保管できる制度が施行されました。閲覧や撤回もできるため、資産状況や気持ちが変われば何度でも書き直すことができます。遺言者が亡くなると関係相続人に通知が送られる制度が21年度内にも始まる予定のため、「遺言書がどこにあるのかわからない」と家族を悩ませることもありません。
なお、終活の一環として浸透しているエンディングノートは、家族へのメッセージや葬儀の希望などを自由に書くことができますが、自筆証書遺言としての法的効力はありません。相続に関わる遺言は、法律に基づく形式で作成することをお勧めします。
確かな遺言書づくりを弁護士がサポートします
メリットの多い自筆証書遺言ですが、法律で定められた様式にのっとっていないと法的効力が失われてしまうため、書き方には注意が必要です。自筆証書遺言保管制度を利用しても、法務局が遺言の内容をチェックしてくれるわけではないので、内容に不備があれば無効になってしまいます。
法的効力のある正しい遺言書を作成するためには、法律のプロである弁護士にご相談ください。札幌弁護士会では、相続問題や遺言に関するご相談に応じています。札幌弁護士会では無料の『法律相談センター』を開設しています。電話で相談日を予約すると、予約した日時に弁護士があなたにお電話。電話にて相談に応じます。まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
無 料 011-251-7730
<受付時間>月~金(祝日除く) 10:00~12:00/13:00~16:00
提供/札幌弁護士会 企画制作/北海道新聞社営業局