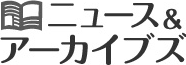この仕事につく前のことを話すのは少し恥ずかしいのですが、私は学生時代に麻雀とパチンコにどっぷりとはまり、学業そっちのけで夢中になっていた人間でした。
その後、「このままではいけないと思い、司法試験に合格するために一念発起して全て辞めて合格しました!」となれば少しは格好もつくのでしょうが、現実はそう甘くなく、司法試験を始めても数年くらいは辞められず、勉強の合間、というより始める前に逃避をして、下手の横好きであったことからそのたびに極貧生活を続けておりました。
せっかくアルバイトで稼いだお金を、勉強に専念するためと言い訳をして、一発逆転を夢見て勝負に出て、余計にアルバイトを入れることになりさらに勉強が遅れるなどという人間でした。
そうしたアルバイトの中では、今から思えば労働基準法がどこか違う国の法律であるかのような職場で仕事をしたこともあり、中には深夜になると時給が下がるという不思議な勤務先もありました(夜間割増分の支払いを実質的に免れるためです)。
最終的には一切を断ち切り、何とか合格することができたので、それらしい顔をして今は仕事をしているのかもしれません。
けれども、この仕事について相談者のお話を聞く中で、同じようにギャンブルに填ってしまった方、お金がなくて苦しい思いをしている方、ひどい労務環境に苦しんでいる方とお話しさせて頂く機会があります。
その中で、普通の弁護士より肌で感じる部分があることがあったようにも思いますし、自分にとって内緒にしている過去ですが、意外なところで活きることもあるのだなと思ったりもしました。
ところで、法律家になるための試験である司法試験については、司法改革がなされる中で、平成16年4月に設立されたロースクールを原則として卒業した上で受験することになりました。
その改革の理由の中には「多様な人材を確保する」ということが目標にあったと聞いております。
確かに、多様な人材が法曹界に入ることで、様々な分野について法律家が携わることが出来るのは良いことだと思います。
しかし、様々な事情があり、現在はそうした結果にはなっておりません。
むしろ多様な人材どころか、ロースクールにかかるお金や、合格後の司法修習が給費は出ずアルバイトとか出来ない中で1年間受けなければいけなくなるなど、むしろ目指す人には一定の条件が必要になっているようにも思えます。
弁護士の中にはなってから非常に努力をして様々な分野に関わってきた方も多数おり、必ずしもなる前に多様である必要があるのかなということは疑問に思いますし、何よりも、私はロースクールが条件になる直前に合格したのですが、同期を見ると会社員を辞め一念発起した人や、夫を亡くしてから社会に何か還元できることをと思って始めた人、元プロスポーツの選手だった人、漁師だった人など、などなど前からも多様で十分ではなかったかと思います。
また、先ほど私はギャンブルに填ってしまった方に肌で感じている部分があったと言いますが、必ずしも分かっている人が相談することが良いとは限らない場面もあると思います。
そんな種類のことを多様とは言っていない!と偉い方から怒られそうですが、そもそも「多様」というのは非常に曖昧で、どこまでの範囲なのかなと思わずにはいられません。
他にも専門家との連携や詳しい方との連携を改革していくことで多様な問題に対応できることもあると思います。
私はこの一連の司法改革に十分知識があるわけではないので、どうこう述べる立場ではないのですが、広く利用しやすい制度を作っていく努力は絶対必要ですし、これまでに足りない部分が法曹界にあったからこそ改革という話が出たのでしょうから、改革していかなければならない部分があることはその通りだと思います。
ただ、一連の話を聞く中で、一度決めた制度だからということで固執しているようにも見える部分があります。
大事なことは広く利用しやすい制度を良い法律制度を作るということなのであり、結果として予想と違ったこと、うまく行かなかった部分は勇気をもってやり直すということにしてもらいたいと思っています。
2012/05/01
【隔週一言】「多様」とは?