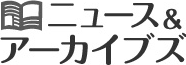5月下旬、日弁連と関東弁(関東弁護士会連合会)、近弁連(近畿弁護士会会連合会と道弁連(北海道弁護士会連合会)の合同調査に参加して、ドイツ・ベルリン等を訪問してきました。道弁連記念大会シンポジウムの準備のためです。
 ドイツが再生可能エネルギー拡張に用いている手法は、再生可能エネルギーで電力を生産したら、電力供給会社が必ずこれを買い取らねばならないという手法(フィードインタリフ)です。具体的に言うと、 1991年 電力供給法 Stromeinspeisungsgesetz 2000年 再生可能エネルギー法(EEG)の2法が決め手となり、両法律によって、電力供給会社は、送電線との接続と固定価格で20年間買い取ることを義務づけられました。これにより誰でも、計画的に電力生産者になれることになったのです。そして、自分で風力発電や太陽光発電をすれば、確実に利益を得ることができるようになったのです。
ドイツが再生可能エネルギー拡張に用いている手法は、再生可能エネルギーで電力を生産したら、電力供給会社が必ずこれを買い取らねばならないという手法(フィードインタリフ)です。具体的に言うと、 1991年 電力供給法 Stromeinspeisungsgesetz 2000年 再生可能エネルギー法(EEG)の2法が決め手となり、両法律によって、電力供給会社は、送電線との接続と固定価格で20年間買い取ることを義務づけられました。これにより誰でも、計画的に電力生産者になれることになったのです。そして、自分で風力発電や太陽光発電をすれば、確実に利益を得ることができるようになったのです。
この制度は、実は、補助金などは一切使われていません。
買取によってその分電気料金が上がりますが、それは国民が等しく負担するということになります。さらに、もっと正確に言えば、大電力消費地である都会の人々がたくさんの負担をして、それを発電を沢山する過疎地が利益として受け取るという冨の再分配が行われることを意味していると思います。
電力を作る特定の企業や原発を立地している特定の市町村だけというように、狭く厚く利益を分配するのではなく、もっと広く薄く利益を再分配するという制度なのです。
再生可能エネルギーは、単純にお金だけを生み出すのではありません。
建設やメンテナンスで地元に雇用を生み出します。私が訪問した旧東ドイツのダルデスハイムでは、30基余りあるウィンドファームの管理を地元の若者8名のクルーで管理しています。それを、ウィンドファームを作る条件としたというのです。また、修理や建設に必要なものは周囲の地域から調達することを決めていますし、基金に出資参加できるのは地域の人に限定もしているのです。
 再生可能エネルギー設備で、確実に利益が上がることから、広く個人や地域が再生可能エネルギー施設を建設した結果、短期間に大きな発電装置を建設したのに等しい効果を生み出しました。
再生可能エネルギー設備で、確実に利益が上がることから、広く個人や地域が再生可能エネルギー施設を建設した結果、短期間に大きな発電装置を建設したのに等しい効果を生み出しました。
特に、太陽光発電は、今問題となっている電力消費時のピーク時に逆に発電量もピークに達するため、むしろ、昼間は電力が余ってしまうような状態が作り出されています。
このため、今ドイツでの課題は、日中作り出された過剰な再生可能エネルギーをいかに蓄電して夜間に生かすかというものです。
すなわち、ドイツの今の課題は、蓄電なのです。蓄電技術の競争が今行われています。

ちなみに、同シンポジウム「再生可能エネルギー基地北海道」~北海道のあらたなる可能性~は、来る2012年(平成24年)7月20日(金)午前9時~12時 ロイトン札幌3Fで開催されます。入場は無料です。