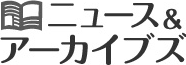弁護士会には,いくつも委員会があり,私は,2つの委員会に所属しています。私が所属している委員会のひとつが子どもの権利委員会です。
毎年,当会子どもの権利委員会では,子どもの日記念シンポジウムを行っています。今年は,子どもシェルターをテーマにシンポジウムを行いました。
子どもシェルターとは,虐待で家に居られない,帰る場所がない等子どもの緊急避難場所です。現在,全国8都県で子どもシェルターが設立されています。
上記シンポジウムにおいて,全国で初めて民間の子どもシェルターを作ったNPO法人(現在は社会福祉法人)の理事長にご講演いただき,また,パネルディスカッションでは,児童養護施設の施設長と自立援助ホームの施設長をお招きし,お話を伺いました。
パネラーの方の「見ようとしなければ見えない。」という言葉が印象的でした。私は,これまで弁護士をしている中で,子どもシェルターの必要性を強く感じたことはなかったのですが,過去に私が少年事件の付添人として,関わった少年の中で,子どもシェルターがあったら,違う道を辿っていた子がいるかもしれません。「家にいたくない。」という子どもの言葉を単なる甘えと思って聞いていたのですが,その子にとっては,親と離れて暮らしてみるのが一番良かったのかもしれません。その子のことを見ていなかったことを痛感しました。
誰にも相談できずに生きることに苦しんでいる子が札幌にもいるはずです。
もちろん,シェルターの設立にも運営にも福祉関係,医療関係の方々やその他関係各機関の協力は不可欠です。
ただ,子どもシェルターには,親権との対峙という問題と設立運営費というお金の問題があり,前者については,特に弁護士の力が発揮できるところであり,後者についても上記シンポジウムで講師を担当された方や既に運営されている子どもシェルター関係者の方々が行政と交渉し,一定の条件のもとに国庫補助を受けられるようになりました(それでも国庫補助は,子どもシェルターの運営費の1割程度にすぎず,不足する部分については,毎年子どもシェルターを運営する各法人が,個人,企業,団体に働きかけ,寄付金や助成金を受け賄っているようです。)。実際に,全国8都県にある民間子どもシェルターの設立,運営には弁護士が深く関わっており,日弁連では,子どもシェルターの公的制度化を求める意見書を提出しています。
当会でも子どもの権利委員会が中心となって,こどもシェルターの設立に関する取り組みを開始しています。私も弁護士会の一員として,少しでも力になれればと思っています。
2012/08/15
【隔週一言】子どもシェルター