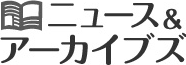私は「韓流」ドラマ・映画は殆ど観ないのですが、最近、「華流」、すなわち、中国の映画を良く観ています。
日本の歴史物も、もちろん面白いのですが、日本の歴史に関する記録は紀元後700年くらいに編纂された「日本書紀」が最古ですから、約1300年程度しか遡ることができません。
一方、中国は紀元前500年くらいからの歴史をもとにした物語があり、「三国志」等は日本人にもファンが多い物語です。
そして、中国の歴史物語には、多くの故事成語が残されており、その多くは日本人にも馴染みの深いものです。
今日は、その中の一つ、「臥薪嘗胆」を取り上げます。
私自身も、この言葉の意味を薪の上に寝て、肝を嘗めて我慢するという程度の知識しかなかったのですが、この言葉には、大事を為すためには、時間がかかるため、根気が必要であるという意味が含まれていることを最近知りました。
紀元前500年頃、これまた「呉越同舟」という言葉で有名な「呉」という国の王様「夫差(ふさ)」と「越」という国の王様「勾践(こうせん)」という人がおりまして、夫差は父の仇(勾践)を討つために、国力を養いながら、薪の上に寝て、その宿願を忘れないように心掛け、やがて、越を滅亡寸前まで追い詰めます。
一方、夫差に降伏し、夫差の召使になった勾践は、国に戻されると毎日、肝を嘗めて、復讐を誓い、降伏してから12年後に挙兵し、やがて夫差を自殺に追い込み、呉を滅ぼします。
このような復讐合戦が良くないことは当然ですが、この故事成語は、大事を為すために必要なものは、「忍耐×時間」ということを教えてくれます。
私たちが日々行っている訴訟は、長いものですと数年かかり、気が遠くなることもあるのですが、夫差と勾践の忍耐力を見習って根気強く進行していかねばと考える次第です。
2012/04/01
【隔週一言】臥薪嘗胆