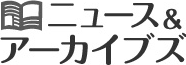執筆:堀江 健太 弁護士
親から「どんなに頼まれても他人の借金の保証人には絶対なるな」と言われたことのある方は多いのではないでしょうか。
保証には、単なる保証と連帯保証の2つがあります。連帯保証と保証では連帯保証の方が責任は重いのですが、どう違うのかと言いますと、具体的には2つあります。
一つは、保証の場合、もしお金を貸した人がお金を借りた本人に請求せずに、いきなり保証人に請求してきた場合、まずはお金を借りた本人にちゃんと請求して下さい、と言うことができます。これに対し連帯保証の場合、お金を貸した人は、いきなり連帯保証人に請求することが可能です。
もう一つは、保証の場合、お金を借りた本人が返済する能力があって、財産もあるという場合には、まずお金を借りた本人から回収して下さいと言うことができます。これに対し連帯保証の場合、お金を借りた本人に収入や財産があろうとなかろうと、いきなり連帯保証人から回収ができます。
このようにまずはお金を借りた本人に、と言うことができる保証人と違い、連帯保証人になる、ということはお金を借りた本人と同じ責任を負うということを意味しています。その点を「連帯」という言葉で表しています。
とはいえ、保証人に請求が来る場合というのは、お金を借りた本人に請求しているけど、お金が無くて払えないと言われているというような状況なのがほとんどですので、そうなってしまうと保証と連帯保証に特に差はありません。
なお、民法が改正され、2020年4月から保証に関する規制が追加されました。
改正前は、賃貸借契約の保証人など、保証人となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するのかがはっきりしない場合(「根保証契約」と言います)でも、保証人の責任に限度はありませんでした。改正後は、根保証契約において保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効となります。
このように保証人を保護する規制はありますが、保証人が重い責任を負うことに変わりはありませんので、保証契約をするときは慎重に判断しましょう。