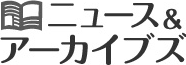執筆:小荒谷 勝 弁護士
総務省の「令和5年通信利用動向調査」によると、日本のインターネット利用者は86%に達し、スマートフォンの保有率も約8割に及びます。SNS利用者も8割を超え、インターネットやスマートフォンが日常生活に欠かせない存在となる中、電子書籍やネット銀行、ネット証券、バーコード決済、暗号資産といったデジタル化された財産も急速に広がっています。
それでは、これらの「デジタル財産」は相続の対象となるのでしょうか。
民法第896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と規定しています。この規定に基づき、デジタル財産も相続の対象となりますが、いくつかの留意点があります。
まず、民法上の所有権は、物理的な「有体物」を対象とするため、デジタルデータそのものは所有権として相続することができないと考えられます。一方で、デジタル財産に関連する権利や契約が相続の対象となる場合があります。ただし、SNSのアカウント等について、利用契約で「被相続人の一身に専属する」と定められている場合は、相続の対象外となるケースが多いです。
また、相続においては負債も承継の対象となるところ、例えばサブスクリプションの料金やFX取引で生じた負債があれば、これらも承継する可能性があります。
さらに、デジタル財産特有の課題として、存在や所在が目に見えにくい点が挙げられます。被相続人が利用していたデジタル財産の情報を相続人が把握できない場合、遺産分割を適切に行えない可能性があります。
これらの課題に対しては、遺言書を活用することが有効です。遺言書にデジタル財産の所在や内容を明記しておくことで、相続人がスムーズに対応できるようになります。
プライバシーの観点から、死後に不要となるデジタルデータを消去したいといった場合は、死後事務委任契約を結ぶことで、必要な財産を引き継ぎつつ不要なデータを適切に処分することも可能です。
もし対応にお困りの場合は、ぜひお近くの札幌弁護士会法律相談センターでご相談ください。
以上