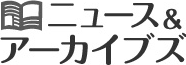執筆:鍛冶 香織 弁護士
(以下、日高報知新聞に掲載されたものです。)
誰でもいつか必ず相続人、被相続人となる日がやってきます。しかし、その準備を怠ると、残された家族間に予期せぬ争いを生む可能性があります。ご自身にもしものことがあった時のために「遺言」の作成をおすすめします。
遺言は、故人の最終的な意思を法的に示すものであり、法定相続に優先されます。遺言を作成することで、誰に何をどのように相続させるかを具体的に指定できるため、相続人間での無用な争いを防ぎ、故人の想いを尊重した円満な財産承継が可能になります。
遺言には主に三種類の方法が存在します。
最も一般的で確実なのは「公正証書遺言」です。公証役場の公証人が関与して作成するため、形式不備や内容の不正確さによる無効のリスクが低く、家庭裁判所での検認手続きも不要です。
一方、「自筆証書遺言」は、遺言者が自分で作成するため費用は抑えられますが、形式不備や内容の不明確さから無効となるリスクや、紛失・改ざんのリスク、家庭裁判所での検認が必要となる手間があります。近年の相続法改正により、財産目録の作成負担が軽減され、法務局による保管制度ができたことで、利用のハードルは下がりました。しかし、法務局では保管にあたって民法の定める形式に適合するかの外形的なチェックをするのみで、内容について確認したり助言することはしないため、内容の不正確さによる無効のリスクや、内容の解釈を巡る争いの可能性は依然として存在します。
また、「秘密証書遺言」は、公証人や証人が封筒の中身を確認しないため、遺言の内容を誰にも知られずに作成できます。ご自身で作成するため、費用は公正証書遺言に比べて抑えられます。ただし、形式不備で無効になるリスクや家庭裁判所での検認が必要となる手間は自筆証書遺言と同様にあります。原本はご自身で保管するため、紛失や改ざんのリスクも伴います。
遺言作成にあたっては、財産目録を正確に作成し、誰に何を相続させるかを明確に記載することが重要です。また、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の相続財産の割合)にも配慮する必要があります。弁護士に相談することで、法的なアドバイスを受けながら、より確実でスムーズな遺言作成を進めることができるでしょう。もし、お近くにお知り合いの弁護士がいないのであれば、最寄りの札幌弁護士会の法律相談センターを検索してご相談をしてみてください。