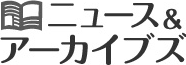執筆:佐藤 敬治 弁護士
犯罪被害者等支援条例をご存知でしょうか。文字通り、犯罪の被害に遭った方や、そのご遺族等を、居住地の自治体が支援するための条例です。
北海道でも、ここ数年多くの市町村で犯罪被害者等条例の制定が進んでおり、令和6年4月1日時点で51の市町村で犯罪被害者等支援条例が施行されています。日高地方でも、浦河町、えりも町、様似町、平取町(五十音順)で令和5年度に犯罪被害者等支援条例が制定されました。
なぜ今、犯罪被害者等支援条例の制定が広まっているのでしょうか。平成17年に施行された犯罪被害者等基本法には、地方公共団体が、犯罪被害者等の支援に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有すると規定されています。
この法律の施行を受けて、多くの地方公共団体において、犯罪被害者等支援のための窓口の設置が進められましたが、具体的な支援策の策定は思うように進んでいませんでした。そのような中で、実際に犯罪の被害に遭った方や、そのご遺族等が支援を求めて声を上げ続けてきたこと、京都アニメーション事件や大阪北新地でのクリニック放火事件など、勤務先、通院先といった日常生活の場において大勢の方が被害を受ける重大事件が発生し、いつ、どこで、誰が重大な犯罪被害に遭ってもおかしくないとことが意識されるようになってきたことなどから、少しずつ犯罪被害者等支援条例の必要性が理解されるようになっていきました。
犯罪被害者等支援条例の内容は市町村によって様々ですが、家事・育児・介護などの日常生活に関する支援、公営住宅への入居や転居費用の助成等の住居の確保に関する支援、カウンセリング費用の助成等の精神的被害の回復のための支援、見舞金の支給等の経済的支援など、様々な施策が定められています。
犯罪の少ない平和な街に住んでいても、通勤先、通学先、通院先、旅行先など、いつ、どこで、誰が犯罪等の被害に巻き込まれてもおかしくありません。札幌弁護士会では、犯罪等の被害に遭ってしまった方を国、地方公共団体、地域住民が皆で支えていくために、北海道内のすべての市町村に犯罪被害者等支援条例が制定されることを目指しています。