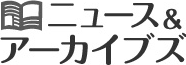執筆:大山 洵 弁護士
(以下、日高報知新聞に掲載されたものです。)
今回は弁護士の「生態系」についてお話します。具体的には、弁護士がどうやって生計を立てているか、などのお金周りのことが意外と知られていないのではと思い筆を取っています。
弁護士の中でも、民間企業に雇用される「インハウスローヤー」と呼ばれる弁護士がいたり、行政の中で任期付きの公務員等として稼働する弁護士が居たりもします。
昨今、こういった弁護士も増えてきてはいますが、多くの弁護士は自営業者として自身で顧客を獲得して売上を立てるか、所属する事務所やその代表の弁護士から固定の報酬や給与を貰う形で稼働しています。特に、前者の形で稼働する弁護士は、自身のお金で弁護士会費、賃借している事務所建物の家賃、雇用するスタッフの人件費…など諸々の費用を支払い、その手残りから税金を控除した額がようやく自分の所に来ることになります。
法律事務所にも様々あり、中には所属弁護士が数百人にも上る大規模な事務所もありますが、弁護士の多くは世の中の小規模な個人商店と同じです。弁護士に税制優遇はなく、確実に売上の一部が填補される医療保険のような制度もありません。
このように、多くの弁護士は日々の売上や経費など経営のことも考えながら、ご依頼いただいた目の前の案件に取り組んでいることになります。
そして、弁護士業は何らかのモノを同時に大量に売るような業態ではなく、弁護士が案件ごとにオーダーメイドで対応する必要があります。そのため、どうしても1人の弁護士が対応できる案件数には限りがあり、さらに先ほどお話しした弁護士業を行うための経費等を支払わなければならないため、ご依頼に際して決して安くはない費用を頂戴することになります。
他方で、個々の弁護士が毎月拠出する弁護士会費を原資に、弁護士が極めて少ない司法過疎地域に公設事務所が設置されていたりします。また、国選弁護などと異なり、国費は充てられないものの人権救済の必要性が高いと思われる活動に弁護士が関与する場合にも、同様に弁護士会費を原資としてその弁護士に対する報酬を自分たちで支払ったりしています。
今回は弁護士の「生態系」としてお金に関する話をしてみました。これを読んでいただいた皆様に少しでも弁護士のことを知っていただければ幸いです。